なぜ、たった半日で、出血ゼロの支台歯形成が、速く・上手にできるのか?
「補綴の基本」ですが…
支台歯形成は、補綴治療の基本であり、もっとも重要なプロセスのひとつです。日々の臨床で、当たり前のようにおこなう処置だからこそ「基本に忠実に、確実に」。先生も、そう心がけていらっしゃるでしょう。ところが実際には、形成方向に迷ったり、マージンの設定で悩んだり。何度も修正しているうちに、思った以上に削ってしまうこともあります。あるいは、歯肉を傷つけて出血が生じ、視野の確保が難しくなってしまった経験もあるかもしれません。
このようなトラブルは、補綴物の適合不良や脱離、さらには、患者さんからのクレームの原因にもなります。その結果、つい慎重になりすぎて、「形成に時間ばかりかかってしまう」と感じているドクターも多いのが現実です。
きちんと学んできたのに自信が持てない…
「自分の形成は、本当に正しいのか?」。そう感じる瞬間が、先生にもあったのではないでしょうか。もちろん、学生時代には支台歯形成の基本的な知識・技術を学び、模型実習も経験してきたはずです。しかし、実際の臨床では教科書どおりにいかない場面も多いでしょう。症例ごとに微調整を加え、試行錯誤をくり返すうちに、気づけば自己流の形成が定着していた。これは、誰にでも起こりうることです。少し考えてみてください。
マージンの位置、形成軸、バーの選択など。先生は、明確な基準をお持ちでしょうか? ひとつ一つの判断があいまいなままでは、どうしても「このくらいでいいだろう」という感覚に頼った形成になってしまいます。実際、「形成に時間がかかる」「形成軸が安定しない」といった悩みの多くは、こうした判断のあいまいさが原因となっているケースが少なくありません。
速く・上手な支台歯形成を「120分」でマスター
本教材のテーマは、「速く・上手に支台歯形成をすること」です。補綴のエキスパートである小林先生の46年分の知見をギュッと凝縮し、支台歯形成における最重要ポイントだけを「たった120分」でわかりやすく学べるよう構成しました。単なる理論・手技の紹介ではありません。大学では教えてくれない「臨床の勘所」を、リアルなデモとわかりやすい解説で習得できる、実践特化型の教材です。
「形成に時間がかかる」「上手に形成できない」「自己流を見直したい」。もし先生が、こう思われるなら、本教材は間違いなく、今後の臨床に役立つ「学び直しの転機」になるはずです。先生も、支台歯形成の不安・迷いを、確かな技術とロジックで払拭しませんか?
大学では教えてくれない「支台歯形成の極意」が学べる120分の動画セミナー。その収録内容とは…?
- 切削器具と切削器械のメリット・デメリット
- 支台歯形成時の歯髄傷害(温度上昇)
- 冷却に影響を与える「4つの因子」とは?
- 接触圧と、切削効率・温度の関係
- タービンのコントロールのポイントと注意点
- タービンのコントロールの実演
- どのタイプのマージン形態がいいのか?
- 支台歯のテーパーに影響を与える因子
- 支台歯の形成軸は?
- 歯の位置異常がある場合の形成のポイント
- もし、支台歯の形成軸を誤ったら?
- クリアランスの確認のポイント
- 骨縁上組織付着とは、何か?
- 骨縁上組織付着と歯の種類の関係
- 歯間乳頭の存在の有無
- マージン設定時に考えるべきポイント
- マージン位置が歯周組織に与える影響
- マージン設定位置の基準とは?
- 縁下マージン設定のガイドライン
- 縁下マージン設定の実演
- タービンヘッドを固定するポイント
- どうやって、ガイドグルーブを設定するのか?
- 口蓋側軸面と舌側面の形成のポイント
- 32年経過した長期の歯周補綴症例
- 上顎右側中切歯の形成の実演
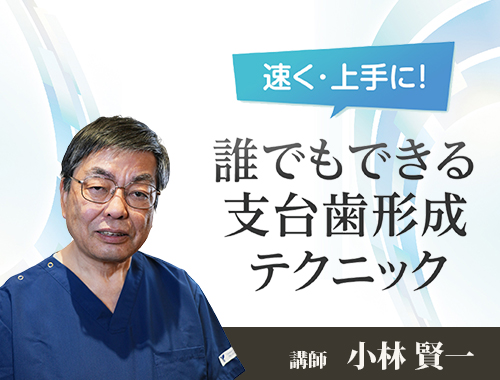
※ご購入後すぐに、このページで本編をご視聴いただけます
- 収録内訳
- 4セクション(合計129分収録)
- 特典
- レジュメデータ
- Sec1:支台歯形成の要点(57分)
- はじめに/切削器具と切削器械/支台形成時の歯髄傷害/タービンのコントロール/クラウンのマージン形態/支台歯の維持および抵抗形態/支台歯の形成方向/支台歯のクリアランスとその確認/
- Sec2:支台歯と歯周組織の関係(34分)
- 骨縁上組織付着/マージンの設定位置/外科的処置後の歯周組織の反応、治癒期間/エビデンスに基づいた支台歯形成/
- Sec3:タービンのコントロール-上顎前歯部-(24分)
- タービンのコントロール-上顎前歯部-/32年経過長期症例/
- Sec4:上顎右側中切歯のデモ(14分)
- イニシャルプレパレーションタービンの持ち方・薬指の筋トレ/終わりに/
講師:小林 賢一
1979年、東京医科歯科大学歯学部を卒業後、同大学大学院(歯科補綴学)を修了。その後、東京医科歯科大学で助手や講師を歴任し、1994年からテキサス大学サンアントニオ校補綴科に留学。1996年から2011年まで、同校の臨床准教授を務める。2019年に東京医科歯科大学を定年退職し、2024年に虎の門病院歯科嘱託医を退職。「総義歯臨床の押さえどころ」「チェアサイドにおける義歯修理の押さえどころ」「支台歯形成と咬合の基本」など、著書多数。
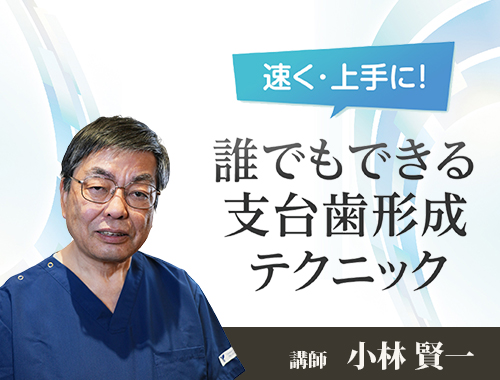
なぜ、たった半日で、出血ゼロの支台歯形成が、速く・上手にできるのか?
「補綴の基本」ですが…
支台歯形成は、補綴治療の基本であり、もっとも重要なプロセスのひとつです。日々の臨床で、当たり前のようにおこなう処置だからこそ「基本に忠実に、確実に」。先生も、そう心がけていらっしゃるでしょう。ところが実際には、形成方向に迷ったり、マージンの設定で悩んだり。何度も修正しているうちに、思った以上に削ってしまうこともあります。あるいは、歯肉を傷つけて出血が生じ、視野の確保が難しくなってしまった経験もあるかもしれません。
このようなトラブルは、補綴物の適合不良や脱離、さらには、患者さんからのクレームの原因にもなります。その結果、つい慎重になりすぎて、「形成に時間ばかりかかってしまう」と感じているドクターも多いのが現実です。
きちんと学んできたのに自信が持てない…
「自分の形成は、本当に正しいのか?」。そう感じる瞬間が、先生にもあったのではないでしょうか。もちろん、学生時代には支台歯形成の基本的な知識・技術を学び、模型実習も経験してきたはずです。しかし、実際の臨床では教科書どおりにいかない場面も多いでしょう。症例ごとに微調整を加え、試行錯誤をくり返すうちに、気づけば自己流の形成が定着していた。これは、誰にでも起こりうることです。少し考えてみてください。
マージンの位置、形成軸、バーの選択など。先生は、明確な基準をお持ちでしょうか? ひとつ一つの判断があいまいなままでは、どうしても「このくらいでいいだろう」という感覚に頼った形成になってしまいます。実際、「形成に時間がかかる」「形成軸が安定しない」といった悩みの多くは、こうした判断のあいまいさが原因となっているケースが少なくありません。
速く・上手な支台歯形成を「120分」でマスター
本教材のテーマは、「速く・上手に支台歯形成をすること」です。補綴のエキスパートである小林先生の46年分の知見をギュッと凝縮し、支台歯形成における最重要ポイントだけを「たった120分」でわかりやすく学べるよう構成しました。単なる理論・手技の紹介ではありません。大学では教えてくれない「臨床の勘所」を、リアルなデモとわかりやすい解説で習得できる、実践特化型の教材です。
「形成に時間がかかる」「上手に形成できない」「自己流を見直したい」。もし先生が、こう思われるなら、本教材は間違いなく、今後の臨床に役立つ「学び直しの転機」になるはずです。先生も、支台歯形成の不安・迷いを、確かな技術とロジックで払拭しませんか?
大学では教えてくれない「支台歯形成の極意」が学べる120分の動画セミナー。その収録内容とは…?
- 切削器具と切削器械のメリット・デメリット
- 支台歯形成時の歯髄傷害(温度上昇)
- 冷却に影響を与える「4つの因子」とは?
- 接触圧と、切削効率・温度の関係
- タービンのコントロールのポイントと注意点
- タービンのコントロールの実演
- どのタイプのマージン形態がいいのか?
- 支台歯のテーパーに影響を与える因子
- 支台歯の形成軸は?
- 歯の位置異常がある場合の形成のポイント
- もし、支台歯の形成軸を誤ったら?
- クリアランスの確認のポイント
- 骨縁上組織付着とは、何か?
- 骨縁上組織付着と歯の種類の関係
- 歯間乳頭の存在の有無
- マージン設定時に考えるべきポイント
- マージン位置が歯周組織に与える影響
- マージン設定位置の基準とは?
- 縁下マージン設定のガイドライン
- 縁下マージン設定の実演
- タービンヘッドを固定するポイント
- どうやって、ガイドグルーブを設定するのか?
- 口蓋側軸面と舌側面の形成のポイント
- 32年経過した長期の歯周補綴症例
- 上顎右側中切歯の形成の実演
講師:小林 賢一
1979年、東京医科歯科大学歯学部を卒業後、同大学大学院(歯科補綴学)を修了。その後、東京医科歯科大学で助手や講師を歴任し、1994年からテキサス大学サンアントニオ校補綴科に留学。1996年から2011年まで、同校の臨床准教授を務める。2019年に東京医科歯科大学を定年退職し、2024年に虎の門病院歯科嘱託医を退職。「総義歯臨床の押さえどころ」「チェアサイドにおける義歯修理の押さえどころ」「支台歯形成と咬合の基本」など、著書多数。
- 収録内訳
- 4セクション(合計129分収録)
- 特典
- レジュメデータ
- Sec1:支台歯形成の要点(57分)
- はじめに/切削器具と切削器械/支台形成時の歯髄傷害/タービンのコントロール/クラウンのマージン形態/支台歯の維持および抵抗形態/支台歯の形成方向/支台歯のクリアランスとその確認/
- Sec2:支台歯と歯周組織の関係(34分)
- 骨縁上組織付着/マージンの設定位置/外科的処置後の歯周組織の反応、治癒期間/エビデンスに基づいた支台歯形成/
- Sec3:タービンのコントロール-上顎前歯部-(24分)
- タービンのコントロール-上顎前歯部-/32年経過長期症例/
- Sec4:上顎右側中切歯のデモ(14分)
- イニシャルプレパレーションタービンの持ち方・薬指の筋トレ/終わりに/
