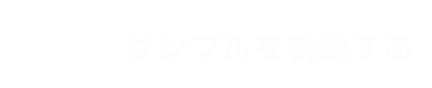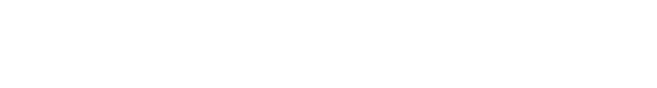なぜ、DH主導のシンプルな評価と訓練で、初回検査から580点を保険算定できるのか?
保険診療メインなら、無視できない治療ですが…
2018年に保険収載された「口腔機能低下症」ですが、先生は、もう導入されましたでしょうか? 高齢者だけでなく、中年者にも多くの患者さんが存在することから、2022年には、適応範囲が65歳以上から50歳以上へ拡大されました。
口腔機能低下症に対応している歯科医院の数には諸説ありますが、2024年現在で、歯科医院全体の10~15%程度と言われています。この数字だけをみると、「まだ様子見かな」と考える先生も多いのかもしれません。
しかし今、口腔機能が生涯の健康において重要であるという認識は、すでに歯科の分野を飛び越え、医科・介護施設だけでなく、一般にも広がりはじめています。事実、一部の歯科医院には、口腔機能低下症で来院する患者さんが急増中。
口腔機能低下症を切り口に医院のイメージアップをおこない、保険収入アップ、自費成約率アップ、継続来院の患者獲得などの成果を得ています。時代が求めるニーズの高い治療を一足先に導入し、先行者利益をひとり占めしている状況なのですが…
診療報酬が手厚くなった今がチャンス
先生もご存じのとおり、令和6年度歯科診療報酬改定で、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)が廃止され、口腔管理体制強化加算(口管強)が新設されました。 そして、口管強の新設にともない、口腔機能低下症を診断するための口腔機能検査にも、いくつか変更された部分があります。たとえば、咀嚼能力検査と咬合圧検査は、これまで6月に1回算定可能でしたが、今回の改定で「3月に1回」に変更されました。 また、口腔細菌検査2(65点)も新たに保険収載となりました。
つまり、口管強の施設基準を満たした上で、50歳以上の患者さんに初回検査をおこなった場合の一例を挙げると、舌圧検査(140点)、咀嚼能力検査1(140点)、口腔機能管理料(60点)、歯科口腔リハビリテーション料3×2(100点)、歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算(90点)、口腔管理体制強化加算(50点)で、合計580点を算定可能になったのです。
治療は一回で終わるものではありませんので、口腔機能低下症を導入すれば、継続的に来院する患者さんをたくさん蓄積できますが…
60代の6割、70代の8割が見込み患者です
もし先生が、「口腔機能低下症は面倒くさそう」「時間がかかるだけで、採算が合わなさそう」「検査・評価方法がわからない」など、こう思われているのなら? この動画セミナーで学べる内容は「まさに先生のためのもの」です。なぜなら今回、口腔機能低下症の導入に関する疑問、不安を朝日大学の谷口先生がすべて解決してくれるから。
約3時間の動画セミナーでは、口腔機能低下症の医療知識・保険算定の方法・検査・評価・診断・改善トレーニング・管理の実務が、オールインワンで学べます。口腔機能低下症の考え方は、歯周病管理とほとんど同じですので、すでに歯周病治療の体制が築かれているのなら、すぐに導入できます。
先生も、「口腔機能低下症」を導入し、さらなる保険収入アップを目指しませんか?
- なぜ今、口腔機能管理が求められているのか?
- なぜ、摂食嚥下障害が生じるのか?
- 低栄養患者の口腔内は、どうなっているのか?
- 「全身」で口腔機能低下を見極める方法
- 口腔機能低下の「前」を知る方法
- 口腔の衰えで見極める方法
- なぜ、口内炎が重要なのか?
- 令和6年度歯科診療報酬改定のポイント
- 口腔機能が低下すると、どうなるのか?
- 口腔機能の低下が進行した症例の映像
- 重度口腔機能低下が起こす問題とは?
- 一般歯科医院が介入すべき重症度
- 口腔の衰えを考える重要なポイント
- 口腔機能低下症を導入するポイント
- 口腔機能低下症と歯周病の類似点とは?
- DH主体の口腔機能低下症の管理
- 口腔機能低下症の評価内容
- 保険点数に繋がる効率の良い検査法
- 咀嚼機能低下の評価方法
- 保険算定が可能な検査項目とは?
- 口腔機能低下症で収益を上げる方法
- 口腔機能管理(訓練)の重要なポイント
- 舌骨上筋を鍛えるトレーニング
- 唾液分泌を促進するトレーニング
- 舌口唇運動機能向上トレーニング
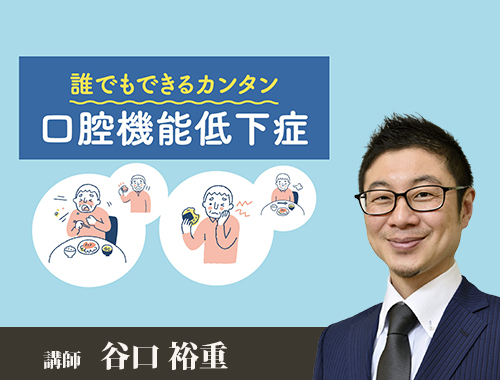
※ご購入後すぐに、このページで本編をご視聴いただけます
- 収録内訳
- 4セクション(合計158分収録)
- 特典
- レジュメデータ ・ 特典映像 ・ 特典データ
- Sec1:口腔機能低下症を見極める3つの方法(40分)
- はじめに/なぜ、口腔機能管理が求められるのか?/①全身を知る/②口腔機能低下の前を知る/③口腔を知る/
- Sec2:口腔機能低下症の3つのポイント(28分)
- ①歯科を知る/②口腔機能低下の後を知る/③全身を知る/
- Sec3:短時間で十分採算が取れる効率的な検査法と保険算定の仕方(48分)
- 口腔機能低下の3つのPoint/①嚥下機能・②咬合力/③舌清掃状態・④口腔乾燥/⑤ディアドコ・⑥舌圧/⑦咀嚼力/保険算定上のポイント/
- Sec4:口腔機能管理~DHもできる指導法~(42分)
- 口腔機能管理(訓練)で重要なこと/トレーニング・唾液分泌促進、保湿/トレーニング・舌口唇運動機能向上/トレーニング・舌筋力向上・咀嚼機能向上/
講師:谷口 裕重
愛知学院大学歯学部卒業後、新潟大学医歯学総合研究科博士課程卒業。その後、新潟大学 摂食・嚥下リハビリテーション学分野 助教を経て、新潟大学病院 摂食・嚥下機能回復部 講師。朝日大学 障害者歯科学分野 准教授、摂食嚥下リハビリテーション学分野 准教授を経て、2023年より教授を務める。
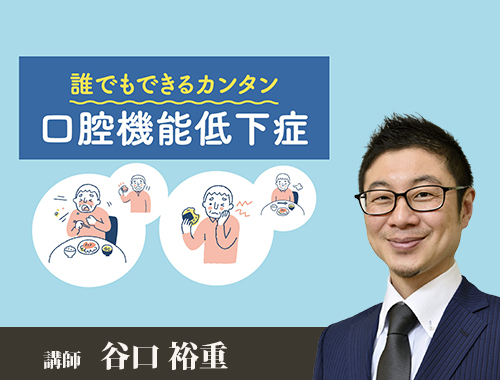
なぜ、DH主導のシンプルな評価と訓練で、初回検査から580点を保険算定できるのか?
保険診療メインなら、無視できない治療ですが…
2018年に保険収載された「口腔機能低下症」ですが、先生は、もう導入されましたでしょうか? 高齢者だけでなく、中年者にも多くの患者さんが存在することから、2022年には、適応範囲が65歳以上から50歳以上へ拡大されました。
口腔機能低下症に対応している歯科医院の数には諸説ありますが、2024年現在で、歯科医院全体の10~15%程度と言われています。この数字だけをみると、「まだ様子見かな」と考える先生も多いのかもしれません。
しかし今、口腔機能が生涯の健康において重要であるという認識は、すでに歯科の分野を飛び越え、医科・介護施設だけでなく、一般にも広がりはじめています。事実、一部の歯科医院には、口腔機能低下症で来院する患者さんが急増中。
口腔機能低下症を切り口に医院のイメージアップをおこない、保険収入アップ、自費成約率アップ、継続来院の患者獲得などの成果を得ています。時代が求めるニーズの高い治療を一足先に導入し、先行者利益をひとり占めしている状況なのですが…
診療報酬が手厚くなった今がチャンス
先生もご存じのとおり、令和6年度歯科診療報酬改定で、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)が廃止され、口腔管理体制強化加算(口管強)が新設されました。 そして、口管強の新設にともない、口腔機能低下症を診断するための口腔機能検査にも、いくつか変更された部分があります。たとえば、咀嚼能力検査と咬合圧検査は、これまで6月に1回算定可能でしたが、今回の改定で「3月に1回」に変更されました。 また、口腔細菌検査2(65点)も新たに保険収載となりました。
つまり、口管強の施設基準を満たした上で、50歳以上の患者さんに初回検査をおこなった場合の一例を挙げると、舌圧検査(140点)、咀嚼能力検査1(140点)、口腔機能管理料(60点)、歯科口腔リハビリテーション料3×2(100点)、歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算(90点)、口腔管理体制強化加算(50点)で、合計580点を算定可能になったのです。
治療は一回で終わるものではありませんので、口腔機能低下症を導入すれば、継続的に来院する患者さんをたくさん蓄積できますが…
60代の6割、70代の8割が見込み患者です
もし先生が、「口腔機能低下症は面倒くさそう」「時間がかかるだけで、採算が合わなさそう」「検査・評価方法がわからない」など、こう思われているのなら? この動画セミナーで学べる内容は「まさに先生のためのもの」です。なぜなら今回、口腔機能低下症の導入に関する疑問、不安を朝日大学の谷口先生がすべて解決してくれるから。
約3時間の動画セミナーでは、口腔機能低下症の医療知識・保険算定の方法・検査・評価・診断・改善トレーニング・管理の実務が、オールインワンで学べます。口腔機能低下症の考え方は、歯周病管理とほとんど同じですので、すでに歯周病治療の体制が築かれているのなら、すぐに導入できます。
先生も、「口腔機能低下症」を導入し、さらなる保険収入アップを目指しませんか?
- なぜ今、口腔機能管理が求められているのか?
- なぜ、摂食嚥下障害が生じるのか?
- 低栄養患者の口腔内は、どうなっているのか?
- 「全身」で口腔機能低下を見極める方法
- 口腔機能低下の「前」を知る方法
- 口腔の衰えで見極める方法
- なぜ、口内炎が重要なのか?
- 令和6年度歯科診療報酬改定のポイント
- 口腔機能が低下すると、どうなるのか?
- 口腔機能の低下が進行した症例の映像
- 重度口腔機能低下が起こす問題とは?
- 一般歯科医院が介入すべき重症度
- 口腔の衰えを考える重要なポイント
- 口腔機能低下症を導入するポイント
- 口腔機能低下症と歯周病の類似点とは?
- DH主体の口腔機能低下症の管理
- 口腔機能低下症の評価内容
- 保険点数に繋がる効率の良い検査法
- 咀嚼機能低下の評価方法
- 保険算定が可能な検査項目とは?
- 口腔機能低下症で収益を上げる方法
- 口腔機能管理(訓練)の重要なポイント
- 舌骨上筋を鍛えるトレーニング
- 唾液分泌を促進するトレーニング
- 舌口唇運動機能向上トレーニング
講師:谷口 裕重
愛知学院大学歯学部卒業後、新潟大学医歯学総合研究科博士課程卒業。その後、新潟大学 摂食・嚥下リハビリテーション学分野 助教を経て、新潟大学病院 摂食・嚥下機能回復部 講師。朝日大学 障害者歯科学分野 准教授、摂食嚥下リハビリテーション学分野 准教授を経て、2023年より教授を務める。
- 収録内訳
- 4セクション(合計158分収録)
- 特典
- レジュメデータ ・ 特典データ
- Sec1:口腔機能低下症を見極める3つの方法(40分)
- はじめに/なぜ、口腔機能管理が求められるのか?/①全身を知る/②口腔機能低下の前を知る/③口腔を知る/
- Sec2:口腔機能低下症の3つのポイント(28分)
- ①歯科を知る/②口腔機能低下の後を知る/③全身を知る/
- Sec3:短時間で十分採算が取れる効率的な検査法と保険算定の仕方(48分)
- 口腔機能低下の3つのPoint/①嚥下機能・②咬合力/③舌清掃状態・④口腔乾燥/⑤ディアドコ・⑥舌圧/⑦咀嚼力/保険算定上のポイント/
- Sec4:口腔機能管理~DHもできる指導法~(42分)
- 口腔機能管理(訓練)で重要なこと/トレーニング・唾液分泌促進、保湿/トレーニング・舌口唇運動機能向上/トレーニング・舌筋力向上・咀嚼機能向上/